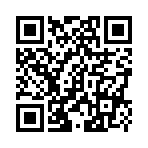2006年07月07日
文楽


文楽は大阪に馴染み深く重要無形文化財にも指定された人形浄瑠璃です。
文楽は物語を浄瑠璃の調べに乗せて語る太夫。それを演奏する三味線。
それにつれて演技する人形が1つの舞台を形成しています。
人形は一体につき三人で操り、頭と右手を操作する主使い。左手とこものを
操作する左使い。足捌きを操作する足使いで構成されています。
<文楽の歴史>
文楽は今から300年以上昔、貞享元年(1684)大阪道頓堀に
人形浄瑠璃芝居のやぐらをかかえた竹本義太夫によって大成されました。
当時としては珍しく人の情愛や喜怒哀楽を語り、
大阪で浄瑠璃といえば義太夫節を指すまでいたりました。
また、忘れてならないのが劇作家の近松 門左衛門である。
この近松 門左衛門は主に世話物で知られ、
「曽根崎心中」は空前の人気をあつめました。
竹本座に続き豊竹若太夫が同じく道頓堀に豊竹座の旗を
あげたのが元禄16年(1703年)である。
両座はそれぞれの異なった芸風で御堂筋を境に東西を分ける黄金時代を築きました。
後に淡路島からでた上村文楽軒によって統合され人形といえば文楽を指すようになりました。
Posted by むーさん at 14:14│Comments(0)
│大阪の文化
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。




 オオサカジンニュース
オオサカジンニュース
 たこ焼きを食べ尽くす
たこ焼きを食べ尽くす
 大阪デートスポット
大阪デートスポット
 電車で行こう!大阪
電車で行こう!大阪
 工場見学へ行こう!
工場見学へ行こう!
 大阪検定合格への軌跡
大阪検定合格への軌跡
 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン