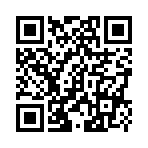2007年01月30日
下寺町
以前紹介した天王寺七坂は上町台地があっただけに?
すこし小高い丘のような場所から松屋町筋の方へ
下る坂が多く見られます。
またこの界隈には寺院なども多く見られ天王寺区全体では
四天王寺、生国魂神社など約200余りの寺院、神社があるらしい。
坂が終わる松屋町筋沿いの下寺町1丁目、2丁目にかけては
たくさんの寺院がずらりと並んでいる。その数25寺院あるそうだ。
25寺院は北から
大蓮寺、称念寺、浄国寺、源聖寺 、金台寺、萬福寺、大覚寺、
光明寺、心光寺、宗念寺、光傳寺、超心寺、西往寺、法界寺、
大光寺、善福寺、宗慶寺、善龍寺、称名寺、西照寺、正覚寺、
幸念寺、西念寺、良運院、円成院。
2007年01月26日
貝塚を歩く
工場見学がてら貝塚駅周辺を散策してみました。
駅から歩いてほどなくすると願泉寺がありました。
が、工事中?らしく何にも見れず…

その願泉寺界隈には古い家が何軒かあり、
国登録有形文化財という看板?標識?がかかっていました。
他にもこのまわりには何軒かあるようで、
それらを寺内町と呼ぶみたいでした。
寺内町という町名なのかとおもっていましたがそうゆう名称で
寺院・道場(御坊)を中心に形成された自治集落のこと。だそうです。
大阪にはこの貝塚以外に
富田林(大阪府富田林市)-興正寺 重要伝統的建造物群保存地区に選定
大ケ塚(大阪府河南町)-顕証寺
久宝寺町(大阪府八尾市)-顕証寺
本町(大阪府八尾市)-大信寺・八尾御坊
萱振(大阪府八尾市)-恵光寺・萱振御坊
貝塚(大阪府貝塚市)-願泉寺
富田(大阪府高槻市)-教行寺
枚方(大阪府枚方市)-順興寺
招提(大阪府枚方市)-敬応寺
(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より。)
こんなにも寺内町があるそう。
さてその寺内町付近をあるいていますと
こんなものを発見!
だんじり自動販売機?どっかの町内会のものなんですかね?
普通はコカコーラとかポカリスエットと描かれている部分が
だんじりの写真でした。
2007年01月23日
大阪検定クイズ⑦

クイズを作っていてまだまだ知らない事がいっぱいだなーと思います。
無知です。
問1 大阪の天六市電交差点で、信号無視をめぐって軍人と警察官が
おこした事件は?
①スクランブル事件②ゴー・ストップ事件③クロスロード事件
問2 945年、首都を飛鳥から難波宮に移し、蘇我氏などの豪族を中心とした
政治から天皇中心の政治へとかわっていった大化の改新が起こった時の
天皇はだれか?
①孝徳天皇②斉明天皇③天智天皇
問3 開業された順は?
①御堂筋線→中央線→四つ橋線→千日前線
②御堂筋線→四つ橋線→中央線→千日前線
③御堂筋線→四つ橋線→千日前線→中央線
問4 明治時代、西日本主要道路の距離計算の起点としてされていた橋は?
①水晶橋②天満橋③高麗橋
問5 織田作之助が愛し、彼の小説「夫婦善哉」にも登場したお店は?
①丸福珈琲店②自由軒③青楓グリル
問6 水の都として知られる大阪の御堂筋には、橋が三つかけられています。
淀屋橋、道頓堀橋、そしてもう一つは?
①大江橋②心斎橋③錦橋
問7 戦前、新世界のジャンジャン横丁の北側に○○劇場という会館があった。
○○とは?
①麻雀②世界③温泉
問8 明治34年に川上音二郎の拠点として建てられ、大阪最初の純洋式劇場は?
①朝日座②大盛座③帝国座
問9 問8の劇場があった場所に現在建っているものは?
①大阪証券取引所②住友信託銀行③淀屋橋センタービル
問10 大阪万博が開催された時、お祭り広場には3つの塔があった。
太陽の塔と母の塔ともう一つは何の塔?
①青春の塔②父の塔③時間の塔
答え←クリック
問1 大阪の天六市電交差点で、信号無視をめぐって軍人と警察官が
おこした事件は?
②ゴー・ストップ事件
問2 945年、首都を飛鳥から難波宮に移し、蘇我氏などの豪族を中心とした
政治から天皇中心の政治へとかわっていった大化の改新が起こった時の
天皇はだれか?
①孝徳天皇
問3 開業された順は?
②御堂筋線→四つ橋線→中央線→千日前線
問4 明治時代、西日本主要道路の距離計算の起点としてされていた橋は?
③高麗橋
問5 織田作之助が愛し、彼の小説「夫婦善哉」にも登場したお店は?
②自由軒
問6 水の都として知られる大阪の御堂筋には、橋が三つかけられています。
淀屋橋、道頓堀橋、そしてもう一つは?
①大江橋
問7 戦前、新世界のジャンジャン横丁の北側に○○劇場という会館があった。
○○とは?
③温泉
問8 明治34年に川上音二郎の拠点として建てられ、大阪最初の純洋式劇場は?
③帝国座
問9 問8の劇場があった場所に現在建っているものは?
②住友信託銀行
問10 大阪万博が開催された時、お祭り広場には3つの塔があった。
太陽の塔と母の塔ともう一つは何の塔?
①青春の塔
他のクイズに挑戦
2007年01月18日
松下幸之助 創業の地
地下鉄千日前野田阪神駅を降り、歩いていると
旗のような看板に「この先松下幸之助 創業の地」というような
類の文字がかかれていたのでちょっとあるいて行ってみると
公園があり、こんな石碑がたっていました。
どうやら、この地大開は、松下電器産業株式会社の創業者松下幸之助が
大正7年(1918年)3月7日に、松下電器の前身「松下電器製作所」
を創立した創業の地らしい。
世界中にその名を馳せた松下は23歳の若さで配線器具や販売を
はじめたそう。
こんなところに創業の地があるとは思いませんでしたが
大阪検定では絶対的に松下幸之助のことが出ると思います。
松下幸之助記念館というのがあるらしいのでいってみたいと思います。
→松下幸之助記念館
2007年01月16日
下水道科学館

阪神電鉄淀川駅にある大阪市下水道科学館へ行ってきました。
淀川駅を降りるとすぐに大阪市海老江下水処理場が
あってそこから10分くらいあるくとこの建物があります。
あまり建物はなくて大きいコーナンが建設中でした。
下水道科学館の前にはちょっと遊べる小道具があり
これはハンドルをまわすとホースから水が出てくる装置。
なんで水がでるのかしばらく考えたんですがわかりませんでした。
なぜ水が出るところは上なのにでるのだろう。いまだ謎はとけず。
館内に入るとひろびろーとしたロビー。
地下で地下探検号というに乗り物がありもうすぐ出発です。といわれたので
地下へダッシュ

空き缶のような乗り物が地下探検号です。映像を見ながら
揺れたりするのです。乗り物によってしまい目をつぶってしまい
全部見れなかったのですがシュタークフォンテン洞窟という
どくろの洞窟など(薄目でみましたがすごかった)
世界の地下を見ることができました。
その後6階へ
エレベーターが空くと素敵な庭。たくさんの緑がありました。
ここは海老江(えびえ)下水処理場で処理された水を使って、
水耕栽培を行っているらしい。金魚もいました。
トマトがなっていました。
5階は展示品やシアターがありました。
ここの展示品は自分で触る事ができて楽しい。
特に見てて飽きなかったのがストロボの光の加減で水が上から下へ
流れているように見えたり水の動きが止まっているように見える展示品。
ふしぎー。
4階は下水道の仕組みのフロアー。
なんも考えなしにこの入口よく見たらトイレの便器やないですか!!
その入口を進んでいくと下水の仕組みがわかる映像がながれます。
他にも豪雨を体験できるスペースや大阪市を大雨の浸水(しんすい)から
守る映像ゲーム(浸水対策ゲーム)です。などがあります。
3階は下水道を学べるフロアー。図書館的なものもありたくさんの下水や
水に関するものを調べる事ができます。
この下水道科学館はただ!そして駐車場も完備なので気軽に行きやすい。
下水道科学館
大阪市此花区高見1丁目2番53号
阪神電車「淀川」駅より徒歩約7分。
TEL.06-6466-3170 FAX.06-6466-3165
営業時間 :午前9時30分~午後5時(ただし入館は午後4時30分まで)
休業日 : 毎週月曜日(月曜日が休日の場合は翌日)、年末年始
料金 : 無料
予約 : 要/10名以上の団体
駐車場 : あり(無料)40台
Posted by むーさん at
14:15
│Comments(2)
2007年01月11日
難波パークスは元米蔵だった
難波パークスは今年4月19日、コンセプトに
「なんば"NEXT"スタンダードライフ」をかかげ
30歳代の男女をターゲットに難波パークス第2期がオープン。
シネコンをはじめ教会を備えた大型レストラン、フィットネス×岩盤浴、
トイザラスなど「衣・食・住」に関わった幅広いお店を出店予定。
さて、その難波パークスの入口付近に「難波御蔵・難波新川跡」の碑があります。
その昔、難波パークスのある辺りには江戸時代に建設された大規模な米蔵と
米蔵から道頓堀を結ぶ運河があったそうです。
●難波御蔵
江戸時代、幕府への年貢米は江戸にいくものと、大坂の蔵に蓄えられるものの
2種類だった。江戸時代中期西日本一帯を中心にイナゴによる大きな被害が
あったこと(1733年 享保飢饉)がきっかけで大坂に幕府直轄の米蔵が設置された。
その後、天王寺御蔵または高津御蔵が難波御蔵に統合され、13,000坪あったという。
●難波新川
難波新川または難波入堀川ともいい、当時は交通の手段として
水路が発展いたので、難波御蔵と建設と共に開削された。
米蔵までは約800メートル、幅約14メートルあり、
運河の端には四方36メートルの船着き場を設けた。
時代を経て、米倉は大阪球場へ、そしてなんばパークスへと姿を変え、
役割を終えた難波新川は昭和に埋め立てられ。現在、川の跡には
阪神高速環状線が走っている。
2007年01月09日
今日から十日戎
商売繁盛笹もってこいっ。で有名な十日戎が今日から始まってます。
今日は宵戎。明日が本戎。明後日が残り戎です。
ということで今宮戎神社に行ってきました!!
大阪にずっと住んでいますが初めての十日戎。
テレビなどで見るだけではすごい混んでいるというイメージでしたが
まだ12時ということもあってまだすいています。
神社に入るとでっかい桶がありここに古い笹を捨てます。
いっぱいになったらこの方たちが持っていってくれます。
境内では商売繁盛の歌?が爆音で流れ、その歌をBGMに
笹を売る売り子さんたちの
「おにーさーん!!笹どうですかー。1500円からですよー。」などという言葉が
飛び交っていました。市場のよう。
お賽銭付近で笹が配られていました。今はまだで笹は余裕でもらえそうでしたが
夜になったらすごい人だかりになるのかしら。
さて、そのただの何の変哲もない笹をもらってここで自分にあった飾りをつけてもらいます。
飾りは小判、俵、お札など様々。
また十日戎といえば熊手!!でも、熊手持っている方は見当たらず。残念。
そうこうしていると献鯛行事という行事が始まり神社に見事な鯛が運ばれてきました。
この献鯛行事は古く江戸時代のから、毎年1月9日に、戎様にゆかり深い
大鯛を奉献し、商売繁盛を祈願しているそうです。また近年は愛媛県青果連の
伊予柑が戎みかんとして奉納されています。
神社の外に熊手やざる?も売られてました。えびすさんがいっぱい。
明日、「十日戎」本戎では、芸者を始めいろいろな方が駕籠に乗り賑やかに神社に参詣
する宝恵駕籠行列が行われます。
Posted by むーさん at
15:12
│Comments(0)
2007年01月05日
大阪出身者
大阪の出身者はたくさんいますがここでは
特に有名な文化人を紹介したいと思います。
川端康成…1899年6月14日大阪市北区此花町生まれ。日本の小説家。
日本人初のノーベル文学賞を獲る。有名な作品に「雪国」
「伊豆の踊り子」があげられる。
清原和博…1967年8月18日大阪府岸和田市出身のプロ野球選手。
現在はオリックス・バファローズ所属。高校時にはPL学園で
活躍し桑田真澄と2人あわせて「KKコンビ」と呼ばれていた。
堺屋太一…1935年7月13日大阪市生まれ。本名は池口 小太郎。
通産省時代に万博開催を提案、1970年の大阪万博で
成功を収める。また小説家でもあり、、『峠の群像』『秀吉』は
大河ドラマの原作にもなった。
司馬遼太郎…1923年8月7日大阪市生まれ。本名、福田 定一。
『竜馬がゆく』『翔ぶが如く』『梟の城』などそれまでの歴史小説
とは少し違った作品を数多く執筆。
俵万智…1962年12月31日大阪府門真市生まれ。
『サラダ記念日』などの歌集やエッセイを中心に出版。
筒井康隆…1934年9月24日大阪府大阪市生まれ。
小松左京、星新一と並んで「SF御三家」と称される。
代表作は『時をかける少女』、『家族八景』、『文学部唯野教授』など。
手塚治虫…1928年11月3日大阪府豊中市に生まれ。漫画家。
医学博士の学位を持ち、それを活かした作品「ブラックジャック」など
数多くの名作を残している。
藤山寛美…1929年6月15日大阪市生まれ。本名、稲垣 完治。喜劇役者。
松竹新喜劇のスターとして活躍した。女優、藤山直美の父。
森繁久彌…1913年5月4日枚方市出身。
NHKアナウンサーを経て俳優になる。代表作に
「屋根の上のヴァイオリン弾き」「佐渡島他吉の生涯」など多数。
与謝野晶子…1878年12月7日堺市出身。作家、思想家。
代表作に「みだれ髪」「春泥集」「新訳源氏物語」など。
和田誠…1936年4月10日大阪府生まれ。イラストレーター。
「話の特集」「週刊文春」の表紙絵を初め数多くの単行本の装丁を手がける。
また、93年「銀座界隈ドキドキの日々」で講談社エッセイ賞を受賞や
「麻雀放浪記」を初めとする映画監督としても知られている。
特に有名な文化人を紹介したいと思います。
川端康成…1899年6月14日大阪市北区此花町生まれ。日本の小説家。
日本人初のノーベル文学賞を獲る。有名な作品に「雪国」
「伊豆の踊り子」があげられる。
清原和博…1967年8月18日大阪府岸和田市出身のプロ野球選手。
現在はオリックス・バファローズ所属。高校時にはPL学園で
活躍し桑田真澄と2人あわせて「KKコンビ」と呼ばれていた。
堺屋太一…1935年7月13日大阪市生まれ。本名は池口 小太郎。
通産省時代に万博開催を提案、1970年の大阪万博で
成功を収める。また小説家でもあり、、『峠の群像』『秀吉』は
大河ドラマの原作にもなった。
司馬遼太郎…1923年8月7日大阪市生まれ。本名、福田 定一。
『竜馬がゆく』『翔ぶが如く』『梟の城』などそれまでの歴史小説
とは少し違った作品を数多く執筆。
俵万智…1962年12月31日大阪府門真市生まれ。
『サラダ記念日』などの歌集やエッセイを中心に出版。
筒井康隆…1934年9月24日大阪府大阪市生まれ。
小松左京、星新一と並んで「SF御三家」と称される。
代表作は『時をかける少女』、『家族八景』、『文学部唯野教授』など。
手塚治虫…1928年11月3日大阪府豊中市に生まれ。漫画家。
医学博士の学位を持ち、それを活かした作品「ブラックジャック」など
数多くの名作を残している。
藤山寛美…1929年6月15日大阪市生まれ。本名、稲垣 完治。喜劇役者。
松竹新喜劇のスターとして活躍した。女優、藤山直美の父。
森繁久彌…1913年5月4日枚方市出身。
NHKアナウンサーを経て俳優になる。代表作に
「屋根の上のヴァイオリン弾き」「佐渡島他吉の生涯」など多数。
与謝野晶子…1878年12月7日堺市出身。作家、思想家。
代表作に「みだれ髪」「春泥集」「新訳源氏物語」など。
和田誠…1936年4月10日大阪府生まれ。イラストレーター。
「話の特集」「週刊文春」の表紙絵を初め数多くの単行本の装丁を手がける。
また、93年「銀座界隈ドキドキの日々」で講談社エッセイ賞を受賞や
「麻雀放浪記」を初めとする映画監督としても知られている。
Posted by むーさん at
20:01
│Comments(0)
 オオサカジンニュース
オオサカジンニュース
 たこ焼きを食べ尽くす
たこ焼きを食べ尽くす
 大阪デートスポット
大阪デートスポット
 電車で行こう!大阪
電車で行こう!大阪
 工場見学へ行こう!
工場見学へ行こう!
 大阪検定合格への軌跡
大阪検定合格への軌跡
 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン